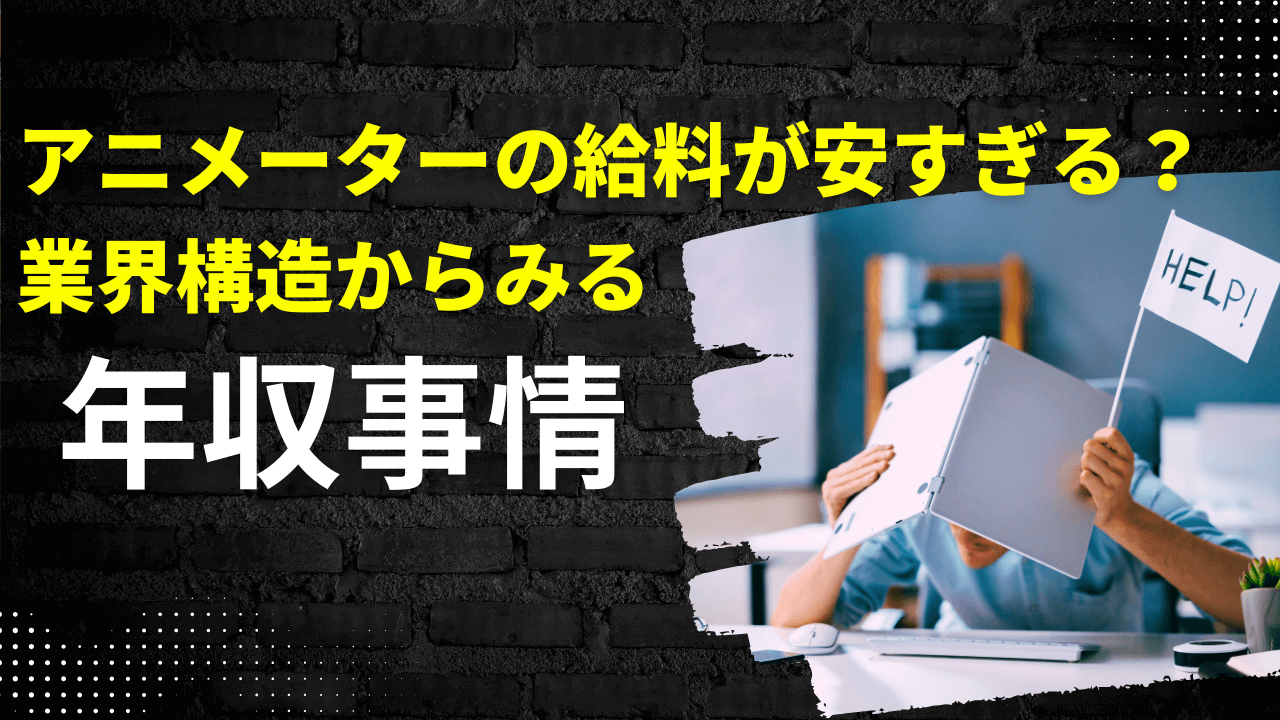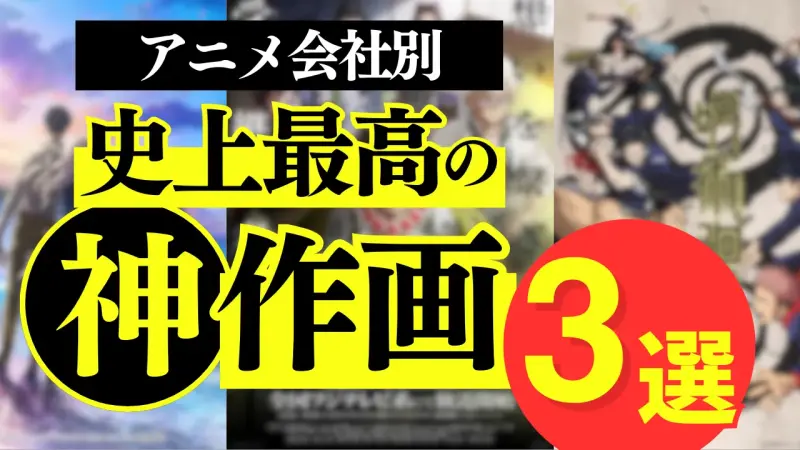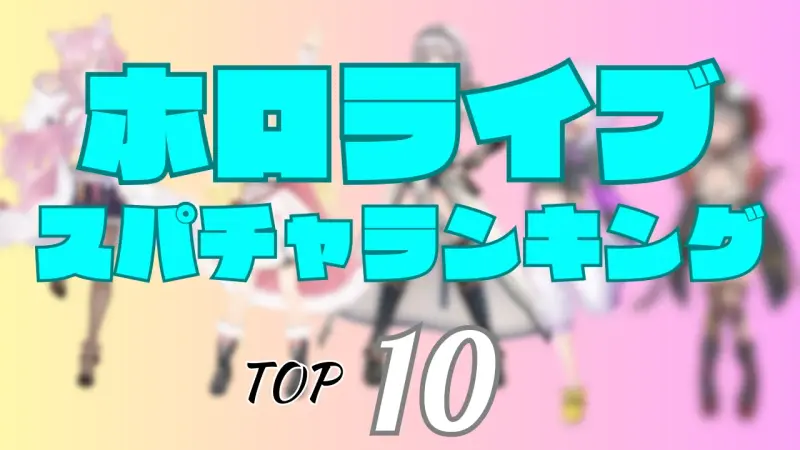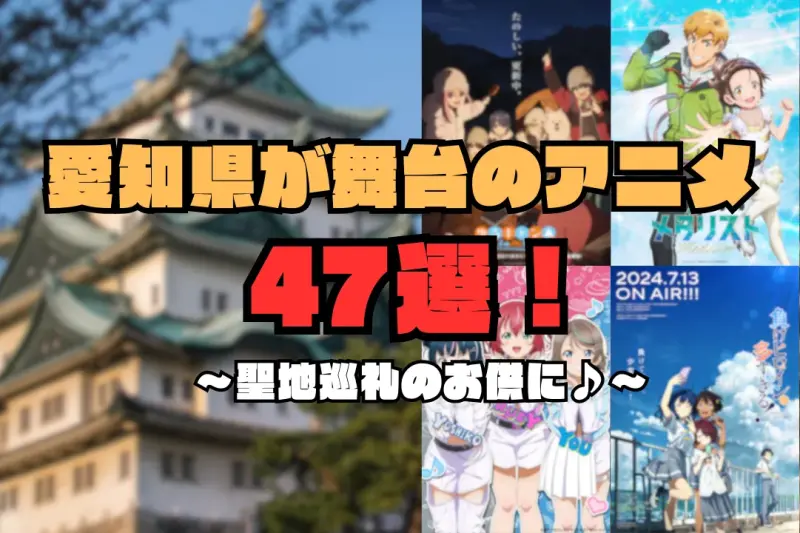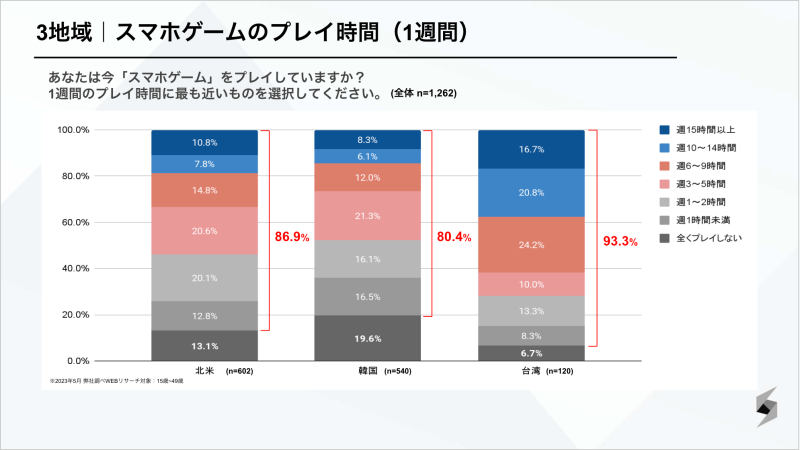日本が誇る一大コンテンツであるアニメ。市場規模は3兆円にまで到達し、今や日本のビジネスを語る上でも欠かせない領域となった。
しかし、業界が盛り上がるにつれ、アニメ業界の低賃金問題も囁かれている。特にアニメーターの給与は新人であればあるほど低く、年収100万円にも満たないという声もある。ここまで低い給与になっているのにはいくつかの理由があるが、一方で
・アニメーター=給料が安い
というのは、「半分正解であり、半分間違いである」という意見もある。
なぜアニメーターの給料は安い(と思われている)のか。業界構造や海外との比較、各調査機関や海外誌の発表したデータなどをもとに紐解いていこう。
アニメーターの給料が安すぎるといわれる背景
業界構造:下請け中心の制作環境
日本のアニメ業界は、製作委員会方式を中心に運営されている。この方式では、複数の企業が出資して制作費を分担し、利益を分配する。しかし、制作会社は予算の大半が宣伝や配信に回される中、限られた資金で実制作を担当する。その結果、アニメーターの報酬が極端に低く抑えられる傾向がある。制作会社の多くは下請けとして機能し、原画や動画を個別に外注することが多いため、直接的な利益が確保しづらい構造となっている。このような構造が、アニメーターの収入が上がりにくい原因の一つである。
単価制の仕組みとその問題点
アニメーターの多くは、出来高払いの単価制で働いている。動画1枚あたりの報酬は200~400円程度と言われており、これではフルタイムで働いても十分な収入を得るのが難しいのが現状である。特に新人アニメーターはスピードやクオリティの面で経験不足なため、1日にこなせる枚数が限られており、月収が10万円以下になることも少なくない。この単価制は、長時間労働を助長するだけでなく、技術向上の妨げにもなりやすい点が問題視されている。
他誌でのアニメーターへのインタビューからは、「1晩徹夜しても得られる収入は2000円程度」「スーパーのレジ打ちをしたほうが稼げる」といった意見もあり、数字だけでは見えにくい過酷さが浮き彫りになっている。
(引用元:レバテッククリエイター)
海外との比較
海外のアニメ制作現場では、日本と異なる給与体系や労働環境が一般的である。例えば、アメリカのアニメーターは年収50,000~80,000ドル(約600万~1,000万円)が相場であり、日本のアニメーターと比較すると大幅に高い収入を得ている。この違いの背景には、海外では労働環境の改善や制作会社の利益配分が進んでいる点が挙げられる。また、海外ではデジタル技術や効率化が進み、制作時間が短縮されていることも、労働条件改善に寄与している。
アニメーターの給与実態と雇用形態の現状
業務委託が多い業界であるという現実
アニメーターの多くが業務委託契約、つまり出来高制で働いている点は既に触れたが、この形態が給与の安定性に大きく影響しているのは明白である。新人動画マンでは1枚あたり150〜250円ほどの報酬であるため、月収5万〜10万円程度に留まるのが実情である。例として、「業務委託だと11万5,298円」という調査結果もあり、そこから社会保険や税金を差し引くと生活は非常に厳しい状況である(新卒初任給:212,658円、業務委託:115,298円)。
さらに、日本アニメーター・演出協会の調査によると、20代前半の若い世代では年収155万円程度とされ、企業勤めであっても初年度の年収が税金の壁に届かなかったという声もある。
平均給与と年収、そして昇給の現実
一方で、中堅層や正社員として所属するアニメーターの報酬は少し異なる傾向がある。JAniCAの実態調査からは、アニメーターの平均年収が約248万円であることが示されている。月20万円ほどを得ているものの、大卒初任給レベルとなっており、ライフスタイルが多様化する年代であることを考えれば、生活は正直厳しい水準である。
もっと詳しく年代別に見ると、20代のアニメーターの平均年収は110万円と非常に低く、若手層の生活状況の厳しさが浮き彫りになる。一方で経験やスキルがあるアニメーターの場合、5〜10年以上で年収500〜700万円程度に達するケースもあり、努力とキャリアアップが報われる可能性もある。
例えば、2D/3DCGを使用した映像制作会社、POINT PICTURESでは新卒正社員の初任給が242,835円(固定残業代30時間分込み)と定められ、年に一度の昇給やボーナス(年2回)、充実した福利厚生が用意されている。これにより、安定した収入と生活を確保できる環境であるといえる。
国内&海外の調査機関が見た給与分布と実態
海外の求人透明化サービスGlassdoorによれば、日本のアニメーターの平均給与は年間278,362円である。また特に高い層では37万8,685円に達することもあり、給与には大きな幅があることが示唆されている。最低水準は21万5,539円であり、経験・実績・契約形態により大きな差が生じていることが読み取れる。
ただ、実態調査では、全体のうち19.4%のアニメーターが年収600万円以上と回答しており、高収入の層も確かに存在する。これは必ずしも多数ではないにせよ、技術力と経験、そして正社員採用や現場内での昇進が年収アップに直結する可能性を示している。
改善への動きと希望の光
業界団体による支援制度:若手育成の取り組み
アニメ業界では、若年層のアニメーター育成支援も進められている。たとえばYoung Animator Training Project(旧Anime Mirai)のように、日本政府の文化庁が支援し、アニメーターの実務訓練を行うプロジェクトは若手の技術向上と待遇改善を目的としている。こうした取り組みは、単なる技能補強に留まらず、アニメーターという職業の持続可能性にも繋がる。
また、一般社団法人日本アニメフィルム文化連盟(NAFCA)では、待遇改善だけでなく、アニメーターのスキルの底上げを図るための資格「アニメータースキル検定」の運営を行っている。これは主に、アニメーターのスキルの土台となる「動画」という分野の技術と知識を測る検定であり、プロのアニメーターになりたい人だけでなく、趣味で絵を描いている人でもチャレンジできる資格だ。
アニメ制作における「動画」の工程は、アニメーターの基礎を高めるうえで欠かせない工程。だが、その工数の多さや制作スケジュールの兼ね合いから、長らく海外に仕事をあっせんしてしまったことで、基礎が身についていないアニメーターも増えているという。待遇のみならず、こういった人材育成の底上げが、日本のアニメ業界への未来につながっていくはずだ。
今後の展望
アニメーターの低賃金問題は長年語られてきた課題であるが、一方で階層や働き方次第では収入改善の余地があることもまた事実である。業務委託から正社員、原画マンから作画監督へ、といったキャリアステップがはっきりしている現場では、報酬も徐々に向上していく。 また、団体や政府による育成・支援制度の活用、さらにはデジタル化と海外展開の推進により、制作効率や予算配分の見直しも期待できる。業界全体としていかにアニメーターの働き方や待遇を改善できるかが、今後のアニメ文化の持続性に直結する重要なテーマである。
“ポップ×カルチャー&ポップ×ローカル”を軸に、アニメ/マンガ/ゲーム/Vtuber/音楽などのエンタメ情報を発信しています。