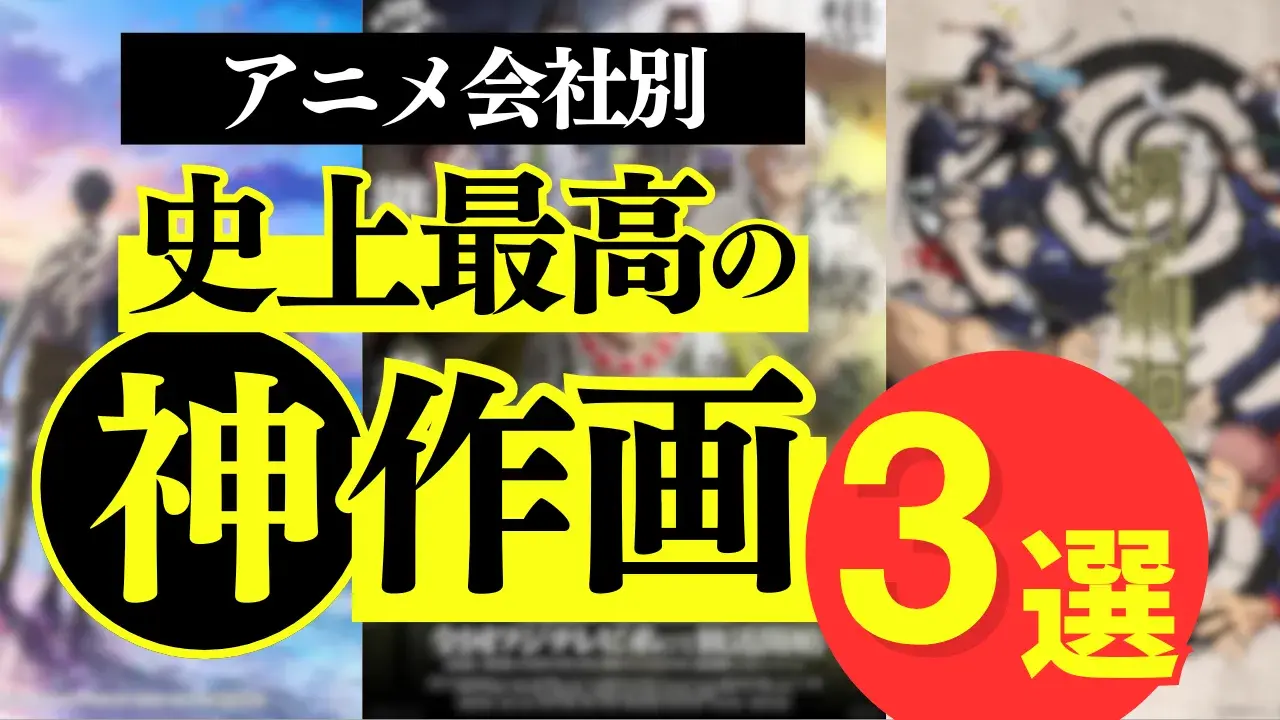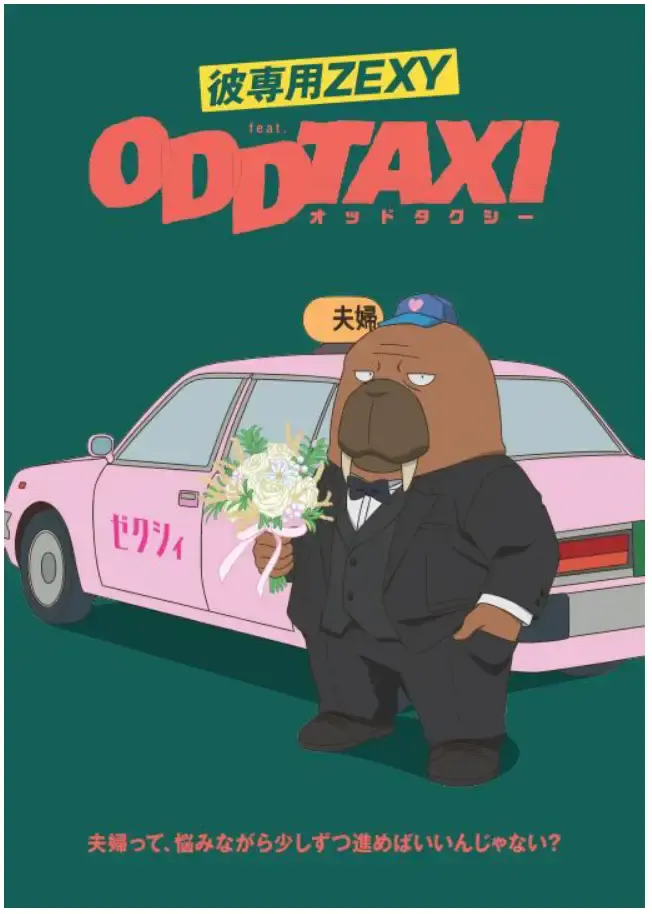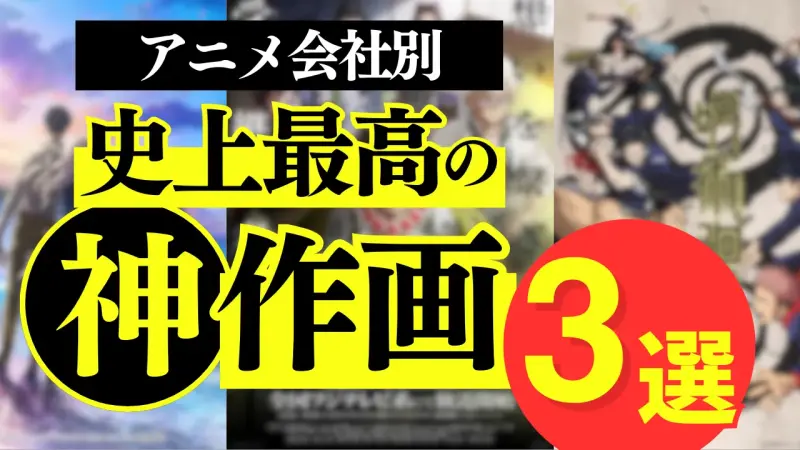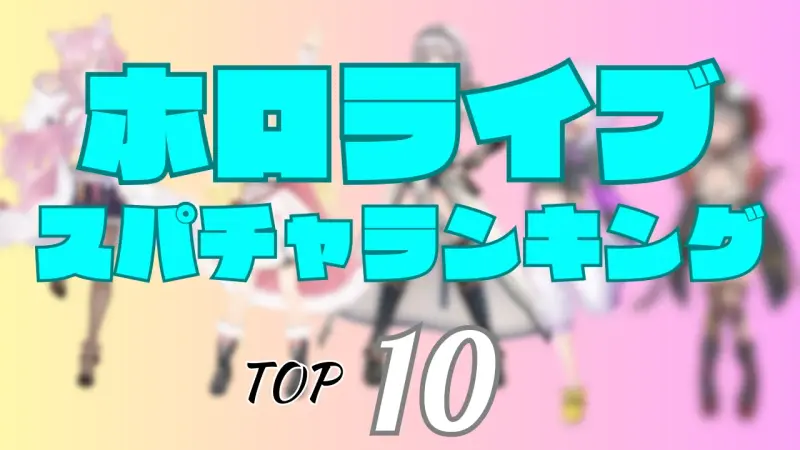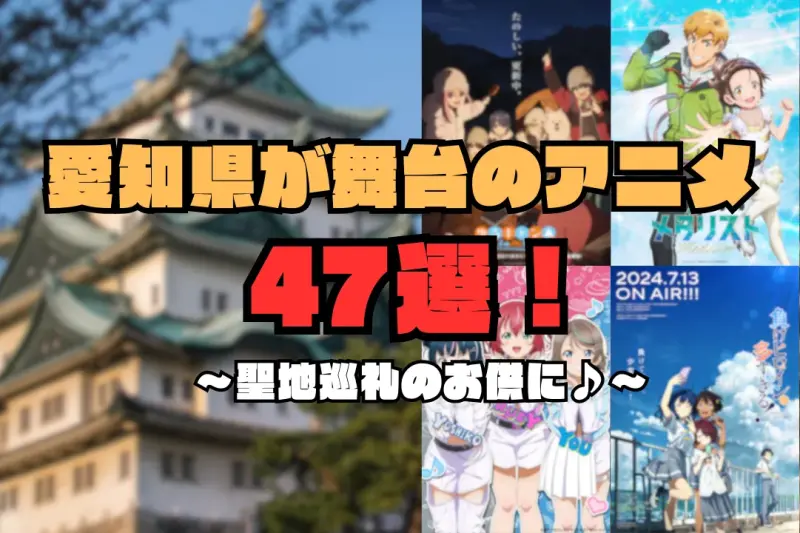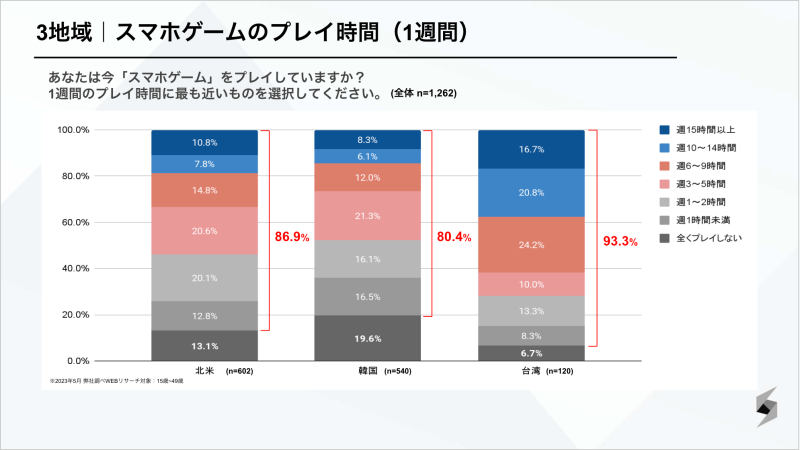アニメ好きであれば、「神作画」という言葉を耳にしたことがあるはず。「映像が別次元にすごい」「画面がめっちゃぬるぬる動く!」といった意味合いだ。一口に作画といえど、そこにはレイアウト・エフェクト・撮影・音までが一体になって爆発した瞬間を指すことが多く、厳密には「作画」ではないが、没入感のある映像を総じて「神作画」ということが多い。
この記事では、編集部独自の観点と市場での評価を参考に、直近で放送されたアニメから往年のアニメまでの代表例について、3つのアニメスタジオの“得意技”から辿っていこう。
ufotable『鬼滅の刃』炎が画面を割る!
まず初めに挙げるのは、今や社会現象となった作品『鬼滅の刃』。制作会社はユーフォーテーブル有限会社(以下、ufotable)だ。
ufotableが鬼滅の刃において見せた強みは、なんといっても派手なエフェクトの表現。手描きの炎・雷・血しぶきを、デジタル合成を用い、微細な粒子を漂わせながら表現することで、ここ一番見せ場がさらに映えるような見せ方になっている。そして、これらをカメラとうまく同期させることで、観客の視線を一切迷わせていないのだ。
また、炭治郎の“ヒノカミ神楽”に見られるような刀に宿る炎の軌跡は、常に斜めに走らせることで刃の“入り”と“抜け”を強調。なおかつカメラはそれを追い越さず、半歩うしろから肩越しで追従する演出が多い。また、背景のトーンを落とし、炎色の彩度を一段上げる色設計も効いている。斬撃や炎がどこから起き、どこで収束するか…に視線を置くと、その表現力がより鮮明になるはずだ。背景のコントラストの切り替え(暗転から→発光など)、そして劇中の効果音が映像と同期し、いわば「音が走る」ような見せ場を可能としている。
観るならこの回!
- 『鬼滅の刃』立志編 第19話「ヒノカミ」 炭治郎の“ヒノカミ神楽”が初めて爆ぜる回。炎と水の軌跡が「×」字に交差するレイアウトで、カメラは肩越し→俯瞰→寄りへと三段切り。父の記憶→技の覚醒→トドメという感情の段取りが、光量の上昇と完全に連動します。最初に“作画お化け”を体感するのに最適。
- 『鬼滅の刃』無限列車編(TV版)最終話「心を燃やせ」(または劇場版) 煉獄杏寿郎VS猗窩座の**「打→受→反」の三拍子が、炎尾の太さと露出の上下**でリズムを刻む。炎の軌跡が画面を斜めに割り、煙の渦が視線を次カットへ橋渡しするので、速いのに迷わない。咆哮で音が“抜ける”一瞬も忘れずに。
- 『鬼滅の刃』遊郭編 第10話「絶対諦めない」〜最終話 炭治郎・善逸・伊之助の連携と、宇髄の火花が三色の軌跡で絡み合う。建物の倒壊を“線の雨”に変える演出が見事で、手描きと3DCGの合わせ目が分からないレベル。切っ先のハイライト→爆ぜる火の粉→暗転の三段で**呼吸の“ため”**を作ってから、一気に解放。
MAPPA『呪術廻戦』スピーディーなバトルシーンでも迷わない、“体感速度”の作り方
今やダークファンタジーアニメが十八番にもなっているのが、株式会社MAPPA。『進撃の巨人』『呪術廻戦』などバトルアニメ御用達スタジオとなったが、彼らの凄みはアニメ内の見せ所を連続して積み重ね、二話、三話と続けてクライマックス級の密度を保つことにある。それを支えるのが、「体感速度」の調整だ。
もう少し具体的に解説しよう。例えば『呪術廻戦』では、呪力を用いて相手を殴ることで、「自分の呪力が漏れ出る」という表現がなされている。素手の打撃や術式の展開、必殺技・黒閃を打つ際に画面に残る残像一つとっても、呪力のエフェクトが畳みかける。そして、激しい肉弾戦ゆえにカメラはめまぐるしく動くが、常にフレームの中心には“顔か拳”が置かれ、視線誘導が徹底されている。そのため、スピードが増しても観客は迷子にならないのだ。
MAPPAの演出でポイントとなるのは“体感速度”の調整といえる。MAPPAは速いだけではなく、速さを感じさせるための“遅いショット”を恐れない。決めゴマの前に一瞬の静止を置き、肩だけを抜いたカットで呼吸を整え、次の爆発で心拍を一気に上げる。そんな、“溜め”と“解放”の設計が、スピーディーなバトルシーンを支えているのだ。
観るならこの回
- 『呪術廻戦』第1期 第19話「黒閃」(京都姉妹校交流会編) 虎杖&東堂VS花御。黒閃の残像が二重露光(1つのフィルムに2つ以上の画像を重ねて撮影する技法)のように重なり、拳の入射角を目で感じられる。パンチの“入り”だけ静かに、ヒットで一気にSEを開く音設計が秀逸!
- 『呪術廻戦』第2期「渋谷事変」連続回(東堂参戦〜宿儺顕現あたり) 二話連続で密度が落ちない“全力走破”。鏡面反射や粉塵まで描き込むのに、顔と拳を中心に据えるから視線が泳がない。
京都アニメーション:水・空気・温度——“触れられる質感”のつくり方
アニメにおいて目立つのは、火と火がぶつかる接戦や、圧倒的なカメラワークで表現される広大さ、キャラが動くときの細かな(いわゆるぬるぬるとした)動きなどが着目される。だが、中でも難しさを極めるのが、水・空気・温度といった自然現象の表現だ。異能力バトルモノで何かしらの自然物を登場させる場合なら別だが、こと自然は丁寧に表現しようとすればするほど、重力や風の流れなど、不規則な事態を予想した作画が求められる。
そんな中、京都アニメーションはこの自然の表現が、他社と比べても頭100個分くらい抜けている。例えば、水泳部の活動と成長を描いたアニメ『Free!』で描かれるレースシーンでは、水面の反射、泡の粒径、水の重さまでを、手描きと撮影の合わせ技で丁寧に再現している。また、リアルさだけを追い求めるのではなく、泳者の腕が水を切ると、泡は前に弾けつつ、腕に沿って後ろへ“擦れて”逃げる。この「前に弾け、後ろに擦れる」が速さの説得力になるよう構成されている。
また、京アニ大賞受賞作でもある『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』の封蝋(ふうろう)が割れる瞬間のロウ、映画『聲の形』などで見られるような、噴水に落ちる光、『氷菓』の夕立で湿る木造校舎…。テクスチャと色彩で、その場の空気そのものを温めることで、触った時の質感を映像に焼き付けることができる。
まさに「触れたくなる質感」がアニメのあらゆる場所に置かれており、目で見るというより身体で納得するのが京都アニメーションの作画の特徴だ。
観るならこの回
- 『Free!』(1期)終盤のリレー回 水面反射→水中の泡→飛沫の尾と主役が交代し、タッチの瞬間だけ音とハイライトが同期。筋肉の皮下でうねる光も描き込み、速さに重さが宿る。
- 『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』第10話(手紙が届くまでの雨の街) 封蝋が割れるロウの粘り、雨粒が紙に落ちて広がる滲み。質感の温度管理が徹底され、感情の温度がそのまま画面の温度になる。
- 劇場版『聲の形』主要シーン(噴水前・夏の光) 噴水の粒子が逆光で虹をうっすらと作る瞬間、音が薄くなる。静けさの中に質感だけが鳴るタイプの“神作画”
作画は“技術”であり“物語”だ
作画の話は、つい線の多さ・影の重ね・枚数といった技術に寄りがち。だが、本当に心をつかむのは、技術が物語と噛み合った瞬間ともいえる。ufotableの炎は、キャラクターが燃やす覚悟の比喩。MAPPAのスピーディーさは、登場人物が限界を超え続ける姿勢そのもの。そして京アニの自然は、触れたいと願う誰かへの距離を描く。 神作画”は、単なる見せ場というだけでなく、その作品が何者で、何を観客に渡したいのかを一枚絵で語る宣言ともいえる。だからこそ、人々の心に刺さるのだ。
やいのやいのと講釈を垂れてしまったが、伝えたいことはただ一つ。難しい言葉はいらない。「今の、やばかった」「マジ凄い」。もう、それだけで十分。そんな瞬間に出会えたら、きっとあなたはもう次の作品を探しているはずだ。
“ポップ×カルチャー&ポップ×ローカル”を軸に、アニメ/マンガ/ゲーム/Vtuber/音楽などのエンタメ情報を発信しています。